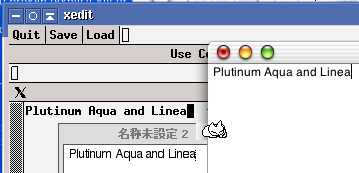
作者には悪いんだけど、CocoaWgetとかAHL-RunnerとかのTerminal系のCocoaアプリケーションはどうにもただの専用Terminalにしか見えない。もっとCocoaらしいガジェットを巧く扱ってユーザーインターフェイスを構築できないんだろうか?
直接には関係ないけど、ちょうどWindowsでVisual Basicが出た時と同じ様に「何でそれがシェアウェアやねん!」と叫びたくなる様なアプリがちまちまと出て来ている。フリーウェアにしても「Cocoaはさっぱり」を読んだそのままのアプリが出て来ていたりする。
会場が美術館えきKYOTOだったので京都駅もじっくり眺めた。……ガメラとイリスの最終決戦場にしてはスケールが小さい……
十年前の恐竜展と言うとバッドランド等のアメリカ大陸産恐竜の標本が主流だったのだが、数年前から中国大陸産の恐竜がちらほらと出始めていて、アルバートサウルスと共にマメンチサウルスががメインで展示されていたりしていた。
今回は重慶の博物館の全面協力と言うことで、展示されているのはすべて中国大陸産。日中友好が功を奏しつつあるのか、はたまた恐竜発掘ラッシュがアメリカ大陸で一段落して中国大陸が遅れて来ただけなのか。
一番興味深かったのは孔子鳥。名前も面白いし、復元図に飾り羽がつけられているのが興味深い。
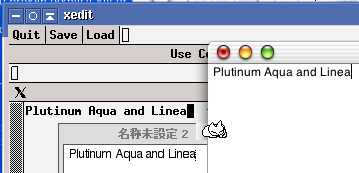
以前GNOMEをFink+dselectでインストールしたのに全然動かなくて、ディスクの肥やしになっただけだったのに懲りてUNIX系統には手を出していなかったのだが、立ち読みした本にaptと言うツールが紹介してあったのでそいつを使ってみた。
GNOMEは大きいので、以前Darwinで試して失敗したXFceをインストールした。……インストールしたのはいいものの、.xinitrcの設定の仕方が皆目分らなかったので、Webで配布しているディストリビューションを直接ダウンロードして中のxfce_setupを実行した。
が、XDarwinを起動しても全く動き出す気配が無い。Consoleに何か残ってないかと調べたら、gdbk_pixbufだか何だかが無いとゴねていた。しょうがないとaptからそれをインストール。NetInfoに何かやったらしいが、とにもかくにも動くようになった。
多言語指向にはCライブラリのものやX11R6のもの等今一つ統一されていないらしい。OS XはCライブラリより一つ上のAPIでずいぶんエレガントに処理しているので問題無いが、(これがTerminalでの多言語思考での問題にもなっていると言う事でもあるが)ざっと見た感じではXFce自体にもいくらか問題があるらしい。
GTK on Quartzが巧く実装されれば、フォントなんかも綺麗に表示できるようになるのか?
Finkってライブラリの依存関係を管理している筈なんだけど、Gdk依存のXFceが何故そのままインストール出来たのだろうか?
基本的にはSolarisのCDEと同じ模様。入っているソフトはXFce付属のものだけなのでほとんど何も出来ないし、何しろ日本語キーボードに問題がありまくりなのでxtermでの操作もおぼつかない。日本語キーボード向けだと言う触れ込みのXmodmapを試したが結果は同じ。OS X標準のキーボードマップがXDarwinでマトモに使える様になるのを待つのが吉か。
一番最初にDockの様に表示される(むしろDockがこの流れを受けたと言うべき)GNOMEでもお馴染みのパレット(正式名称は何だっけ?)だけど、ど真ん中に仮想デスクトップの選択ボタン、その脇にシステム関係のボタン、さらにその外側に各種アプリケーションのアイコンが並ぶと言うこの形、まるで将棋のようだ。確かこのパレットはOS/2が源流になっていたと記憶しているんだけど、真ん中に表示される仮想デスクトップ選択ボタンの意味が最初は全然分からなかった。が、CDEをしばらく使ってみてすぐに理解した。これが無いとまともにウインドウが扱えない。
Windows95(3以前は知らない)はそもそもタスクバーの項目とウインドウが1:1の関係にあるし、Mac OS Classicはアプリケーション・レイヤーによってウインドウがグループ化されているのでウインドウが迷子になる事は少なかった。OS 9からFinderに標準でウインドウメニューが搭載される様になって、アプリケーション内でどれかのウインドウが完全に隠れてしまい迷子になってもすぐに呼び出す事ができる様になった。一方CDEタイプの環境にウインドウをマウスによる直接指定以外で呼び出す方法が無い。この為にウインドウを整理する手段として仮想デスクトップが考え出されたのだろう。
将棋みたいなこの並べ方は、人が真ん中に注目しやすい事と端から二〜三番目の項目を選びやすい事を同時に考慮した面白いインターフェイスだ。ただ、アイコンの項目数や並びの順番等が固定されていたり、アイコンと付属するメニューに実は何の関連性も無かったり、タイトルバーに相当する部分が妙な位置にあったりで問題も多い。
コンクリートブロックの上でトカゲが朱色の花弁を抱く様にしてひなたぼっこをしていた。
その向こうでは雀が草を突いていた。川ではサギがオイカワを突いていた。
カラスがそのサギに喧嘩を売っていた。サギは鬱陶しそうだった。
少し下流の大きなコンクリートブロックで鋪装された場所ではカモが夫婦でブロックの隙間の藻を漁っていた。
帰って来たらトカゲがいなかった。朱色の花弁の淵が茶色くなっていた。
以下の操作は御自分の責任の元で行って下さい。
source /sw/bin/init.cshと言う行を追加する。apt-get updateをかけてパッケージリストを更新。apt-get installでxfree86-base、xfree86-rootless、xfce、gdk-pixbufをインストール。xfce_setupを実行。.commandって拡張子を付けるとダブルクリックで実行してくれるので便利。unset LANGを追加。libxpg4はインストールして、その上で日本語にはlcaledataが必要な事は分かっているんだけど、そこから先が今一分からない。あと、On Mac OS X 10.1, this is required DYLD_INSERT_LIBRARIES to effect on a two-level namespace images.
って一体どう言う意味なんだろう?
もっとエレガントな方法があるよと仰る方は御教授願います。
仮想デスクトップ選択ボタンの左側にiと言うアイコンのボタンがあって、それを押すとXFceのアバウトボックスが表示される。ここまでは何と言う事も無い。右端にはそれにそっくりな、ちょっと影とグラデーションがかかっただけのボタンがある。右端から二番目にはMac OS Xで言うところのパッケージボックスから?マークが飛び出しているびっくり箱アイコンのボタンがある。普通、どちらが何を意味するのだろうか?
右端のアバウトそっくりボタンはxfhelpと言うツールチップ、その隣のびっくり箱のボタンからはxfrunと言うツールチップが現れる。名前から分かる通りxfhelpはヘルプで、xfrunの方はダイアログからコマンドラインを入力するもの。こんな訳の分からん事をするならアバウトボックスとヘルプは一本化してしまうべきだと思うのだが、はてさて。
ちなみに、xfhelpを表示させようとしたらX11用のMozillaが無いとかNetscapeが無いとか泣かれてしまった。Darwin X11用のMozillaやNetscapeなんてニッチなもん存在するんだろうか?
 XDarwinのアイコンはBSDデーモン君の赤とOS Xの
XDarwinのアイコンはBSDデーモン君の赤とOS XのX
のロゴを意識した様なテカリのある画像で非常にいいものだと思うんだけど、いざDockに格納してポインタを併せて拡大したときに淵のジャギが目立ってかっこ悪い。と言う訳で作ってみた。
最初はオリジナルと同じ様に立体的で透明感のあるものにしたかったんだけど、如何せんスキルがついていっていないのでやむなくのっぺりでシンプルなグラデーションのものに変更。128pxを目一杯使ってやる等と言うどこかのオープンソースブラウザみたいな下品な事はせず余白は十分にとり、Mailに習って影も縁取りに近いごく控えめなものを適用。
目分量で測った形を方眼紙に書いたので、角度や長さがオリジナルのXロゴと微妙に違う。x.orgはそう言う素材の配付とかしていないのかな……
xfhelpの実体はただのシェルスクリプトらしい。で、中身を読んでみると環境変数BROWSERに設定されているコマンドにヘルプHTMLファイルのパスを渡しているらしいと分かる。
ならば環境変数を書き換えれば良い訳だ。幸いな事にAppleはコマンドラインからAquaなアプリケーションを開く為のopenコマンドを作ってくれているので、これを使わない手は無い。XDarwin以外で使う訳でも無いので、.xinitrcとなっているshスクリプトにexport BROWSER="open -a Navigator.app"(NavigatorはChimeraプロジェクトのアプリの名前)を付け加える。
これでFizilla CFM、ChimeraとただでさえダブっていたGeckoブラウザにX Mozillaを加えずとも済む様になった。アンインストールアンインストール。
……aptでアンインストールしてもどうもアプリケーションの残した謎のファイルはあちこちに散らばったままらしい。考えてみればそりゃそうなんだが、Libraryの中をざっと見渡せばそれで済む、と言う感覚に慣れた身としては辛い。あと、ホームフォルダ直下に山ほどドットファイルを作ってくれるのも迷惑。
現時点ではxfceだけをインストールしても何故か依存している筈のgdk-pixbufがインストールされないのと、セットアップスクリプトは/sw/bin/に入っていた。
XDarwinと似た様な環境にClassicがある。どちらもOS Xとは異なる構造のシステムをOS X内で実行する為のものだ。Classicは流石にAppleの全面的なバックアップの元に作られているだけあって完成度は高い。Classicの優れている点は、全く別物のシステムのインターフェイスをシームレスに統合している点にある。
対してXDarwinは、プログラムこそMac専用だがそのインターフェイスはそこらのハードウェアエミュレータと変わりが無い。rootlessモードでClassicと似た様な外観を持たせる事は可能だが、例えば、XDarwinを起動したまま他のアプリケーションに移ってもウインドウがインアクティブな外観にならない。また、ウインドウをAqua、Classic、Auqa、Classicの順に重ねて混在させるような芸当ができない。この二つはウインドウシステムの問題だ。
また、ClassicとOS Xが混在できるもっとも根本的な部分がXDarwin、と言うよりX11R6は異なっている。X11R6が結局Windows3.1と同じコマンドラインの補助手段でしかないので、Mac OSのシステム、アプリケーション、ドキュメント、と言う階層構造と馴染まないので、アップルメニューとDockをスタートインターフェイスとしたOS Xには何らかのラッパが必要だ。
以上、XFceのツールバーをなんとかDockに統合できないかと悩んだ結果。
rc.mineに書いたsource /sw/bin/init.cshが反映されなくて何故.cshrcなら反映するのかと悩んだが、alias.mineやenvironment.mineは問題なく反映されているらしい事が分かりさらに悩んだ。結局、init.cshの目的がパスの設定にあるのを根拠にpathに書いてみたらちゃんと反映された。
どうやら読み込むタイミングに問題がありそうなのだが、それ以上はよく分からない。
ところで、おいらのサイトはMacIEで表示すると横方向へのスクロールバーが表示されるんですが、どなたか原因を突き止めてくれませぬか( ̄△ ̄;。
似た様な配置と横スクロールバーは僕も経験しましたし、他のサイトでもしょっちゅう見かける症状ですが……
IE5:macはCSSで指定されたレイアウト上で幅を内容に併せると言う操作が極端に苦手(仕様書に従うと自然にそうなるけど)なのと、position:fixed/absolute周りで縦方向スクロールバーとの表示領域の調節にバグがあるのとが相まってこうなってます。
一番の近道はwidthを指定する事です。ちょうど題と合致する内容なのでした。
そもそも、視覚整形モデルの絶対配置の非置換要素に関してCSS2に準拠しているレンダラは存在していない。今多くのサイトで使われているフローティングパレット的な配置は、まともにCSS2のそれに従うと親全体を覆ってしまう。
これは、絶対配置に関してもレンダラの負担を軽減する為に枠を用意してそこへテキストを流すと言う原則が貫かれているからだが、その所が仕様書には明記されてない為にshrink-to-fit
な整形がデファクトスタンダードとなっているので、それに併せた仕様(in Errata in RFC-CSS2-19980512)が検討されている。
ちなみに、IE5:macは縦方向にのみshrink-to-fit
に整形する。
Apacheをlocalhostにだけ解放して起動する事って出来るんだろうか? ルータとか無しで。
クラムシェルデザインの波及で誕生したヨーヨータイプ。i was Made in **. my Model No.:**
なんて自己紹介している可愛い奴。知らない人が見たら必ず「これ何?」と聞いてくる事は受け合いだ。その初期モデルのアダプタが、よく言われている断線でヤバくなった。後期タイプのものは補強が施され断線の心配は少ないのだが、PowerBook G3 FireWireと言う最後のクラムシェルPowerBookに付属していたのがこの初期タイプだったのは何かの縁か。
まだそんなに遅くなかったのでヨドバシカメラで物色。既にヨーヨータイプは在庫すら残っておらず、コネクタの形状から考えるとG4専用の四角いアダプタでも使えそうなのだが、店員さんに駄目だと言われてしまった。で、仕方無く3rd Partyの黒い奴を購入。持ち運びに便利
なんて謳い文句が着いているのだが、実際に机に乗せると専有面積はそんなに変わらない。ま、鞄に入れる時に四角い方が便利って事だろう。
実際に使ってみると、
パソコン使うなって突っ込みはバリアで跳ね返す。
XDarwinの外からXアプリを起動するシェルコマンドは分かったので、こいつをスクリプトアプリケーションにぶち込めば良かろうと思って試した。一応、ただのランチャーにはなる。いや、XFceもGNOMEもアイコンのクリックってただのランチャーだから、単にDockにその代わりをやらせた事にはなった。
が、アプリケーションメニューやDockメニュー化らの終了は受け付けず、強制終了してもXクライアントは動き続ける。また、アイコンのクリックで全面に持って来たりウインドウをAquaと混在させたりその他諸々のAquaチックな動作は出来ない。Xアプリに管理しているウインドウを全面に出せだとかそう言うメッセージを送る事が出来るのかどうかよく知らないが、Classicと違ってXDarwinと言う一つのAquaアプリの元でしか動けない点が辛い。いっその事XDarwinのようなXサーバを一つのXアプリラッパ内部で丸ごと立ち上げてしまう事も考えたが、今はやり方がよく分からないし物凄く非効率的そうなのでどうにかならないか。
文書の編集は一時領域に対する操作である為にUndo/Redoの実装は難しくない。が、ファイルシステムの操作、特にファイルやフォルダの生成や削除に関してはファイルシステムの持つストレージと言う永続的な領域に対する操作である為Undo/Redoの実装は、削除したファイルについて全てをキャッシングしていなければならない。今現在コンピュータでポピュラーに扱われているハードディスクを直接叩けるのであれば、このキャッシングに関してはそんなに難しいものではない、が、抽象化されたファイル操作プロトコル上ではそのような訳にはいかない。
蛞蝓を素手で潰す羽目に陥った。
ChimeraメーリングリストでHIガイドラインに関して話題になってた。開発者の人はIB使ってんだからそりゃAppleの問題だ
なんて言っていたんだが、グループボックスの話はIBにはどうにも出来ない話。て言うか、以前も話題になってたし、該当項目を読めば何に文句がついているかは分かると思うのに……
要約すると画面を線で埋めるのは勿体ないんでやたら四角で囲むなって事。ほとんどの場合間にセパレータを入れればよろし、と。
これまでmoo系は一番近い店で発売日一週間後でも入荷していない事が多かったので半分諦めていたのだが、嬉しいかな入荷していた。帰って来て初めて攻略本が同時発売であった事を知る。むむ、明日早速買いにに行かねば。
とは言っても今日発売なのを昨日通りがかった古本屋で知った上、その後数分間は購入せねばとしっちゃかめっちゃかしていた。今日発売なのに(笑)。そのうち本家で扱おう。
本家も更新していないなぁ……
いくつか描いているのだが、どれもこれもラフ画の時点で止まってしまう。
どれも共通して線を決めようとする途中で作業が止まる。線画を作る際にシェイプツールを使うのだが、ある一定の所まで線が固まるとそれ以上決められない。そこから完成に近付けようとすればする程描きたかったものから遠ざかっていく。しかもこれを繰り返しているといびつな形で目が肥えてしまうらしく、最近は線画にかかる前に捨ててしまう事も多い。
所謂CG講座なんかを見るとこの点は既に紙の上でクリアしている人ばかりなので、おそらく世の中の大半の人達はそうなのだろう。